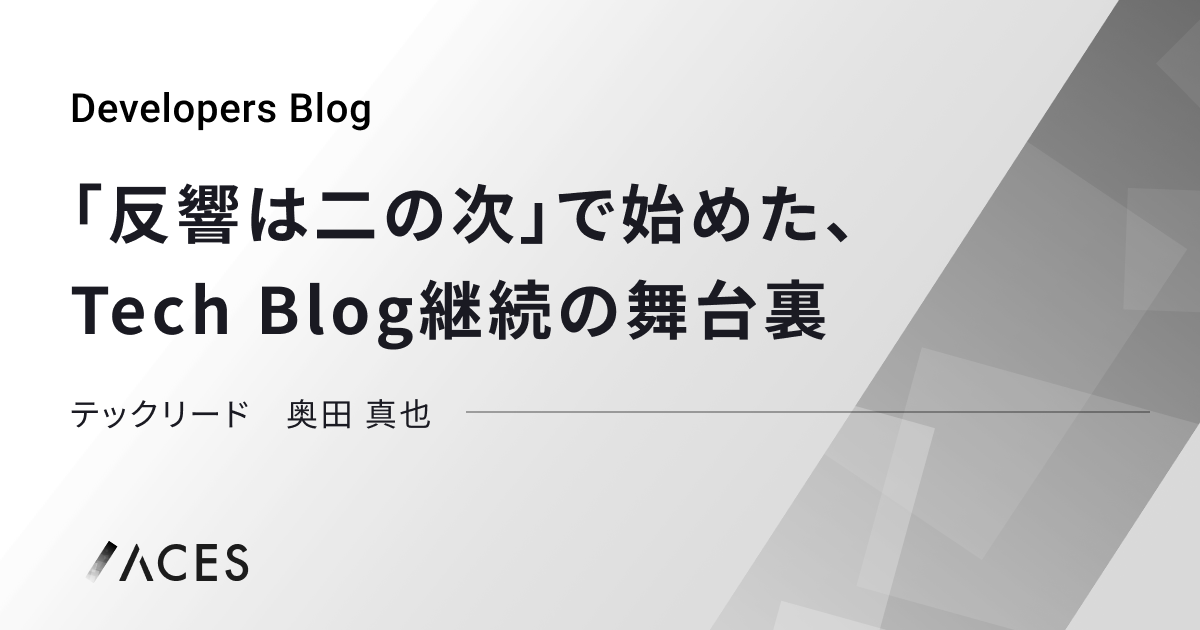 こんにちは、株式会社ACES でテックリードをしている奥田(@masaya_okuda)です。
こんにちは、株式会社ACES でテックリードをしている奥田(@masaya_okuda)です。
私の所属するAIソフトウェア事業部の開発チームはエンジニア7名ほどの1チームなのですが、昨年12月よりテックブログ強化月間をスタートし、本記事が19記事目となります!
多い時は毎週1記事を更新する月もあり、なかなかの更新頻度だと思っています!(上には上がたくさんいますが…😅)
一方でどの開発チームでも、テックブログをもっと運用しようと思った際に一度は、
- 執筆の負担が大きい(他の作業もある)
- 執筆ネタが思いつかない
- そもそも何目的で書くんだっけ?
と、なかなか前に進めないことがあると思います。
本記事では私たちの開発チームが何を目的に、どんな進め方で更新したか?やってみてどうだったか?をご紹介します。
特に、チームリードされているエンジニアの方の参考になれば幸いです。
開発チームの前提と課題
私の所属する開発チームはAI議事録ツール「ACES Meet」を開発しています。ですが会社としてはAIに関する受託開発事業が先行しており、BtoB SaaSの自社サービスを運営する私の事業部の認知度は高くありませんでした。そこでもっと採用強化に繋げるためには?とHowを考えていました。
エンジニアイベントの登壇は機会が限られるため、もっとライトな手段としてテックブログの定期的な更新が候補に上がったのですが、最初はあまり乗り気ではありませんでした。
入社時に1本書いてみた際に非常に時間がかかったため、「本当に継続していけるのか?」と同僚のテックリードに不安をこぼしたことを覚えています。
転機、反響がなくても良いことに気づく
テックブログの運営を考えるにあたり、非常に影響を受けた他社事例をご紹介します。
KINTOテクノロジーズ株式会社
KINTOテクノロジーズ株式会社の上記テックブログは、「反響のある記事を頑張ってかかないと」と思っていた自分には目から鱗でした。この記事の中では、「会社で自分たちがやったことが例え目新しくなくても、会社の外の人には文章で残さないと伝わらない」ことを述べています。
開発チームで強化月間を始める際にも、
- 大きな反響を狙うことはしない
- 特に採用課程で興味を持ってもらった候補者様に、自己紹介するつもりで書こう
と決めました。
ファインディ株式会社
Findy社は特に開発生産性の高い組織としてエンジニア界隈で認知をとっている印象で、思わず頷いてしまう素晴らしい記事や発表資料を多く公開しています。
一方で、各記事よく読むと内容が似た記事もたくさんあります。ではそれを被っていると感じるかといえばそうではなくて、「開発生産性を高めるという文化が会社全体に浸透している」と私は感じました。
私はこれを「テックブログを面で捉えている」のだと思っています。開発チームが本当に大切にしている文化は、言葉を変えて何度でも執筆して良いのです。
テックブログの更新戦略
テックリードの福澤とブログを定期更新する戦略を考えるにあたり、初期構想は以下のような内容でした。
- 私たちが候補者に伝えたい開発文化や目指していることを優先し、反響は二の次
- まずは「ユーザーへの価値提供と技術品質の高さの両方に妥協せず取り組む文化」を伝えたい
- 伝えたいことを網羅的に書いた「親記事」をまずは執筆し、次にその「詳細記事」を書こう
特に、
- 伝えたいことを網羅的に書いた「親記事」をまずは執筆し、次にその「詳細記事」を書こう
は振り返ると非常に良い進め方だったと思います。
設計からリリースまでのプロセスを紹介した記事をまずは執筆し、その詳細なステップをご紹介することでスムーズに執筆できました。
継続することで得た認知、チームへの影響
強化月間はペースを落としつつもまだ継続できており、本記事が19記事目になります。まず継続した成果として、「テックブログをたくさん更新している会社」として勉強会等で認知を実感することができました!
また、たくさん記事を書くとそのうちの何本かは反響をいただくこともできました!
当初の目的でもあった「候補者に私たちの開発文化や大切にしていることを伝える」に関しても、採用面談の最後に候補者の関心に合わせて記事を共有できるようになりました!
AIによる記事執筆のサポート
特に今は生成AIの登場によって、「そもそも記事を人間が執筆するのか?」は私も常々考えます。私は文章を書く際によく手が止まってしまうため、今はChatGPTの音声入力を利用して以下の手順で書くことが多いです。
- 記事にしたい内容を、音声入力で大雑把に話してChatGPTに章構成を考えてもらう
- 章構成がFixしたらChatGPTに共有する
- 章ごとに音声入力で話してChatGPTに執筆してもらう
- 最後に文章を調整
- 完成した文章をブログタイトル生成専用のMy GPTに共有してタイトルを決める
上記の手順で、大体1時間〜2時間ほどで記事を執筆できるようになりました。ここはより効率化したいのですが、「もっとAI活用できるぞ!」という開発チームの事例をお待ちしています🙇!
まとめ
ここまで、1つの開発チームで、半年間テックブログを更新し続けた取り組みについてご紹介しました!個人ではなく企業としてテックブログを運営する際は、
- 記事を書く目的をチームで合意する
- 重要としないことをチームで合意する
- 滑り出しの数記事は戦略を考える
ということを意識すると、チームメンバーを巻き込んで推進しやすいかと思います。
また記事の中でご紹介しましたが、私たちは特に設計時のタスク分解や仮実装に重きをおいて、「ユーザーへの価値提供と技術品質の高さの両方に妥協せず取り組む文化」を大切にしています。他の記事もご覧いただけると幸いです!
本記事を通じてACES Meetの開発チームにご興味をお持ちいただけましたら、ぜひカジュアル面談でお話ししましょう!